4月8日。日経平均歴史的暴落の翌日は歴史的急騰を見せたものの、4月に入ってからの下落分どころか昨日の下落分すら打ち消せていない現状。今回の急騰は一時的な反発(いわゆる戻り目)の可能性も高いため、買いに飛び込むには勇気がいる局面です。
株式投資において「暴落後に急騰する」現象には、いくつかの理屈があります。これは単なる偶然ではなく、投資心理や市場構造に基づいたメカニズムが働いているためです。
1. 過剰な売りによる割安感
暴落時には、多くの投資家が恐怖やパニックにより一斉に売却します。この結果、本来の企業価値に比べて株価が大きく下がる「割安」な状態になります。割安になった株を見た投資家が「安い今こそ買い」と判断し、買いが集中して急騰につながることがあります。
2. ショートカバー(空売りの買い戻し)
暴落局面では「空売り」(株を借りて売ることで値下がりを狙う)をする投資家も増えますが、株価が下げ止まると、空売り勢は利益確定のために株を買い戻す必要があります。この買い戻しが一気に集中すると、需給バランスが崩れて急激に株価が上がることがあります。これを「ショートスクイーズ」とも呼びます。
3. 悪材料出尽くし
株価は将来の不安を織り込んで下がりますが、悪材料(決算悪化や経済危機など)が出尽くしたと市場が判断すると、「これ以上悪くならない」と見て買いが入りやすくなります。期待感の転換によって急騰が起きることもあります。
4. 政府や中央銀行の介入
市場が暴落すると、金融当局(中央銀行や政府)が緊急対策(利下げ、金融緩和、財政出動など)を行うケースがあります。これが投資家の安心感につながり、買いが入りやすくなって急反発することがあります。2020年のコロナショック後のV字回復がその典型例です。
5. テクニカル要因(売られすぎの反動)
テクニカル分析の指標(RSIやMACDなど)で「売られすぎ」と判断されると、短期トレーダーが反発を狙って買いを入れることがあります。これも短期的な急騰を引き起こす一因になります。
◆ 一時反発と本物のトレンドを見分けるポイント
急騰が「一時的なリバウンド」なのか「本格的なトレンド転換」なのかを見極めるには、以下の点が有効です。
① 出来高の動きに注目
- 本物のトレンドは多くの参加者を巻き込むため出来高が増加します。
- 出来高が伴わない上昇は、短期的な反発や機関投資家の一時的な動きの可能性があります。
② 高値・安値の切り上げが起きているか
- 株価が安値を切り上げつつ高値を更新しているかどうかを見ると、上昇トレンドの初期か判断しやすくなります。
③ 移動平均線のクロス
- 短期線が中長期線を上抜ける「ゴールデンクロス」や、移動平均線が右肩上がりに揃う「パーフェクトオーダー」は、トレンド転換の有力サインです。
④ ファンダメンタルズの裏付けがあるか
- 業績の改善、政策発表、新商品など実体のある要因が伴っているときは、本格的な上昇の可能性が高まります。
⑤ テクニカル指標での過熱感をチェック
- RSIが70を超えると過熱とされ、一時的な調整が入りやすくなります。
- MACDのシグナルクロスやゼロライン突破なども参考になります。
このように、「急騰=上昇トレンド」と単純に判断せず、複数の要素を組み合わせて慎重に判断することが、失敗を避けるために重要です。冷静な分析がリターンを最大化する鍵となります。
昨日の暴落時に高配当銘柄を買い増ししなかったこと少々後悔しているのがぶっちゃけなところですが、果たしてあの判断は吉と出るか凶と出るか・・・それは今月中にわかることでしょう。
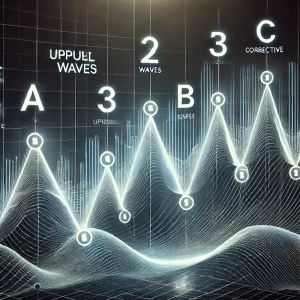
![世界一やさしい スイングトレードの教科書 1年生 [ ロット ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1327/9784800721327_1_2.jpg?_ex=128x128)
![超実践!順張りスイングトレードの極意 損小利大がどうしてもできない人のために [ 荻窪 禅 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7199/9784779127199.jpg?_ex=128x128)
![順張りスイングトレードの極意 最強トレーダーの知恵からボラティリティブレイクアウト活用術まで! [ 荻窪 禅 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6857/9784779126857.jpg?_ex=128x128)

![株でゆったり月20万円。「スイングトレード」楽すぎ手順【電子書籍】[ 尾崎式史 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/9034/2000008179034.jpg?_ex=128x128)
